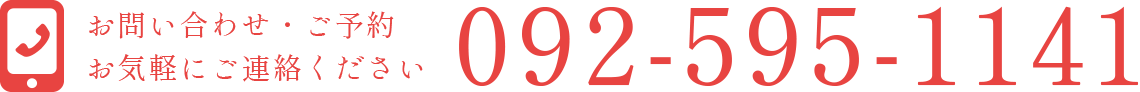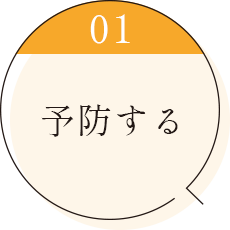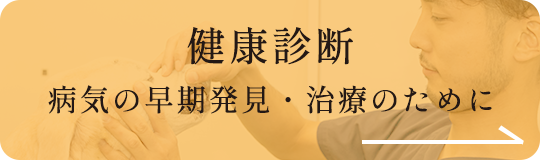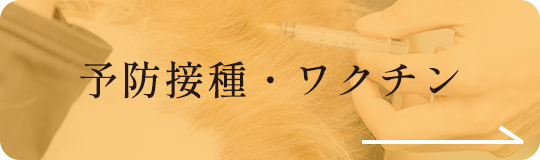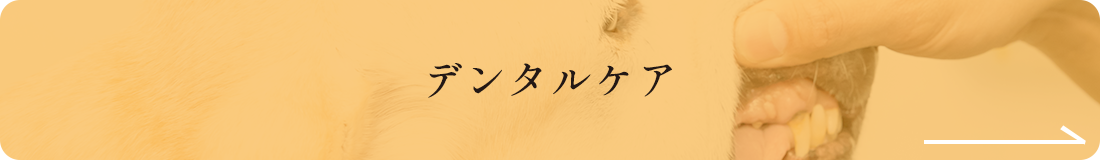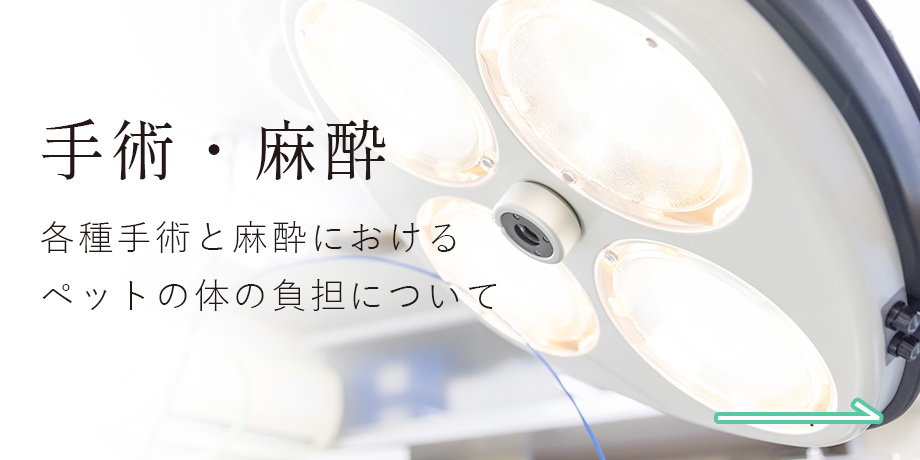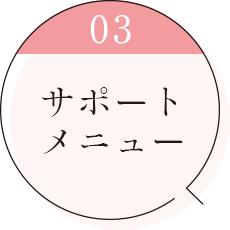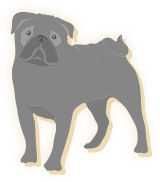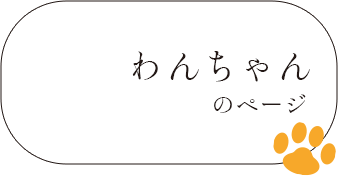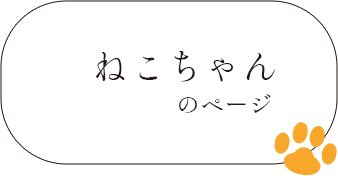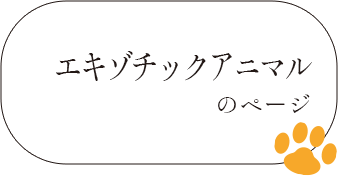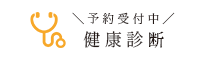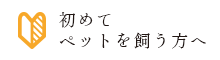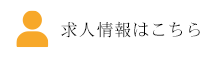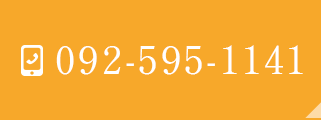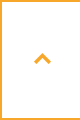GREETINGご挨拶
飼い主様へ

ペットを幸せに
「ハートあるおつきあい」を目指します。
大野城市の動物総合病院ユニベッツ福岡では、爪のケアやカットなどのちょっとしたケアから、腫瘍などの重病まで、トータルにサポートできる環境を整えています。
どんなことでも困ったことがあれば気軽にご相談ください。「ちょっとユニベッツまで出かけよっか」といったような言葉が聞けるような 病院づくりを目指しています。

動物総合病院ユニベッツ福岡では、
欧米などを中心に開催される世界獣医大会に積極的に参加しており、日々進歩していく医療技術を取り入れております。
また、医療行為はもちろん、飼い主様とペットの信頼を深めるため、当院スタッフには懇切丁寧な説明を務めさせております。
気になる事は何でもご相談ください。
FEATURE動物総合病院ユニベッツ福岡について


FEATURE01
的確な診断と適切な処置
動物にとって「より少ない苦痛」を合言葉に、的確な診断と適切な処置を行います。


FEATURE02
予防医療を推奨
治療のためだけでなく、動物が元気で長生きするため予防を行います。


FEATURE03
高度な医療を提供
経験豊富な獣医師たちが困難と言われる手術にも全力を尽くし、高度な医療を提供します。


FEATURE04
丁寧でわかりやすい説明
図や写真等を多用し、わかりやすい言葉で丁寧な説明を行うことに重点をおいています。


FEATURE05
美容メニューを併設
クリニック内にはトリミング室を設けております。高齢や持病があっても安心してメディカルトリミングを受けていただけます。
その他、シャンプーなどの美容メニューも喜んで頂いております。


FEATURE06
生活の質を向上
動物の苦痛がわかる獣医師を育て、飼い主様の意思を尊重する医療を目指しています。